映画は永遠のエンタテイメントであり、教養です。
ぼくたち団塊世代は映画世代です。テレビがまだ一般に普及していない昭和30年代から映画館に通い、ハリウッド映画を観ながら育ちました。たとえば昭和33(1958)年、全国の映画館には11億人の観客が足を運んでいます。当時人口は9000万人だったから、なべて一人年間12回映画館に通ったことになるのです。そのころ全盛だったが西部劇。日本映画では東映の時代劇でした。
ぼくは名古屋の大須で育ちました。大須は当時日本三大繁華街(東京の浅草、大阪の千日前)の一つといわれ、自宅から中学校までの通学路に17館もの映画館が並んでいたのです。
敗戦後、日本はアメリカのGHQの占領下となりました。彼らはそれまでの日本の軍国主義を完全否定し、日本を新たな民主主義国家に改変しました。ぼくらは戦後アメリカの民主主義の指導下に育ちました。
中学生時代、ぼくは西部劇に夢中になりました。西部の男は寡黙で、女性・子供の弱きものに優しく、事件を解決すると風のように去って行く。そんな男たちの背中に感動しました。正義と平和のためには死をも介さず敢然と立ち向かう、そんな男の生きざまに惚れ惚れしたのです。
「リオ・ブラボー」「ワーロック」「ガンヒルの決闘」……何度見直したか数知れません。半世紀経った今でもDVDで見直したりしています。
その後、成長するにつれラブロマンスもの、アドヴェンチャーもの、SFものに趣向は代わってゆきました。あの心躍る西部劇は地上から消え失せてしまったからです。
今は歴史ものを観直しています。名画には数多く歴史ものがあり、映画は世界の歴史を学ぶ、一番手軽で早く、何よりも面白いからです。世界の大歴史を全集で読むならば、途方もなく時間が必要でしょうが、映画なら手軽に学び直しが可能です。
そこでこのコラムはMy Cinema Talkと称して、世界歴史の映画を紹介してゆこうと思います。
旅は歴史を学ぶことからはじまります。
もう一度、世界を学んでみると、また新発見があるかも知れません。
ぜひご一緒に歴史の学び直しをはじめましょう!
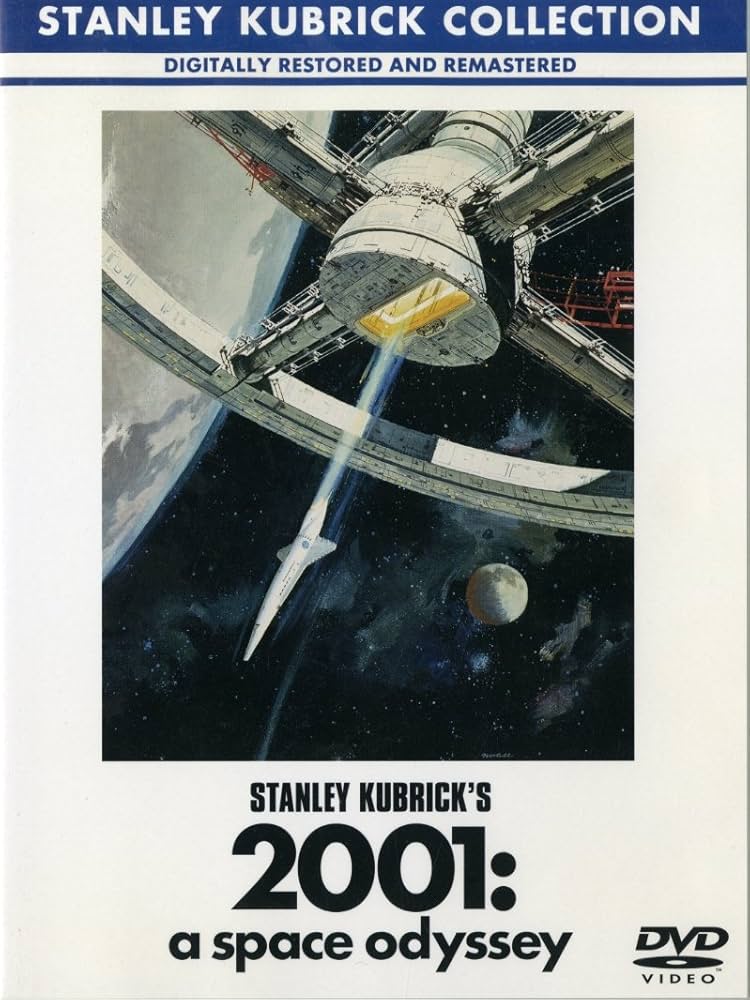
映画は1968(昭和43)年、シネラマで公開された。
この映画の衝撃はいかばかりのものだったか? 映画評論家の双葉十三郎は「これほど壮大な宇宙SFは初めてで、こういう映画を作りあげたキュブリック監督に昔からのSFファンとしてはトロフィーを差し上げたいような気分である」と褒めているが、実際の「ぼくの採点表」(スクリーン誌)での評価は「上出来」のランクに留まり、「四つ星(ダンゼン優秀)」のレベルには達していない。双葉センセイといえども圧倒的な評価には足踏みしたというところだろうか。
公開当時の観衆の評価は賛否両論で、SFながら静的な映画で、退屈。内容がよく分からない、とする意見がある一方、映像が斬新、人類の未来を描いた哲学性に富む傑作と評価は分かれたようだ。
1968年といえばもはや60年も前のことだ。当時はベトナム戦争、学園闘争、プラハの春、キング牧師の暗殺事件と世界は激動の時代だった。とくに米ソの宇宙開発は熾烈を極めており、翌年、1969年7月にはアメリカのアポロ11号が月面着陸に成功、ニール・アームストロング船長の「小さな一歩だが、人類にとって偉大な飛躍だ」の言葉が印象的だった。一方ソ連は1969年1月にソユーズ4、5号による有人宇宙船同士の宇宙空間におけるドッキング、乗員移動に成功している。
映画は木星へ向かう宇宙船ディスカバリー号のなかの事件を扱い、人口頭脳をもつAI、ハル(HAL9000)が宇宙空間の運航途中、頭脳障害から殺人鬼に変ずるというものだ。ハルは冬眠する三人の博士の生命維持装置を外し、二人の乗員のうちの一人を宇宙空間へ投げ捨てるという凶悪犯罪に及ぶ。ひとり残ったボーマン船長はハルに自動開閉装置を拒否され、手動で懸命に船内に戻り、ハルの人口頭脳装置を破壊せしめる。
ディスカバリー号の木星への飛行はなおも継続し、宇宙時間で何万年後、ボーマンが宇宙服のまま現れると、そこは中世の宮殿のようであり、老衰した自らの姿があり、それが息を引き取ると、そこには宇宙の赤ちゃんが誕生する、というストーリーだ。
A Iが日常化している今日からすればHAL9000のコンピューターの巨大装置に違和感を覚えるが、AIにすべてを依存する人間に対して、AIからの復讐の可能性を60年前に警告した映画としてこの映画は現代では最大級に評価されてしかるべきだろう。
このコラムは「人類の世界史」をテーマにしている。
なぜこのSF映画をこのコラムの最初に選んだかといえば、ファーストシーンが人類の祖といわれる猿人からはじまっているからである。猿人を主要なテーマにした映画などほかにないからだ。
サヴァンナの片隅に猿人と鼻の長い牛カモシカとが共存している。
周囲は枯れた平原と岩場で地球の草創期の原風景のようだ。彼らは必至で植物の種のようなものを探し食べている。わたしたちの先祖の猿人はアフリカ大陸に誕生した。彼らが森(ジャングル)を出て、サヴァンナに暮らすことにより、二足歩行が強固なものとなり、それによって脳が発達し、道具を発見することになったという人類史はご存知だろう。
この映画の猿人はまだ二足歩行に至っていない。一見ゴリラのようだ。群れで暮らしており、水場を得るために群同士は戦っている。ある時、群は不思議な石版(モノリス)を見つける。それに触っていると、知恵が芽生え、動物の骨を武器に使うようになった。武器をもった猿人は他の群を水場から追い出す。逆らってきた敵のボス猿を武器であっけなく殺した。人類最初の殺人かもしれない。その猿人が骨の武器を空に投げる。骨(道具)はそのまま宇宙船となり、前述したSFがはじまるという、奇抜な映画のオープニングである。
すでに月面でもモノリスが発見されており、そこから木星へ強烈な電波が発信されている。その事実を確かめにディスカバリー号は木星へ向かうのであった。
このコラムを「2001年、宇宙の旅」からはじめたという意図がお分かりいただけたと思う。猿人を主人公にした映画などないから、この映画を世界史を紐解くオープニングとして登場させたのだ。つまり、このコラム「ぼくの世界史、映画の旅」は猿人からはじめ、宇宙開発までの壮大な人類史を綴ってゆく予定なのである。
かつてタンザニアのオルドヴァイ渓谷を訪ねたことがあった。
タンザニアのほぼ中央、ンゴロンゴロ保護区の近くにある野外化石公園だ。そこは化石人骨の宝庫で、“人類のゆりかご”と呼ばれている。
訪れたのは1983年のことで、まだ観光地にはなっておらず、森の中に掘立小屋がポツンとあるだけだった。陽気な黒人のガイドは「化石はめったに見つかるものではありません」と言いながら「アンモナイトや昆虫の化石はころがっている」という。「ほら、こちら」と連れてゆかれたところは切り立った断崖の下で、河原が広がっていた。
「持ち帰るのはダメですが、転んでポケットに入ったものは致し方ありませーんね」と、足元の小石を指さした。見ると貝殻の化石のようである。なんとも好奇心に駆られ、ポケットに突っ込むと、すかさずガイドはウインクし、掌を差し伸べてチップを要求した。
なあ~んだ。最初から仕掛けられていたのだ。ポケットの化石は本物かどうか、おそらく別のところで仕入れ、ここへ事前にばら撒いたものだろう。まぁよくわからないが、チップを渡しそのまま土産物にすることにした。
今はそんな事はないだろう、と思う。博物館ができて、誰でも化石標本を見られるようになったからだ。
は、ともかく、オルドヴァイ渓谷では、1959年にイギリスのリーキー博士夫妻が、175万年前といわれるアウストラロピテクス・ボイセイ(猿人、石器を使っていた)の人骨を発掘し、1964年には同博士がホモ・ハビリスの化石を発掘した。われわれの祖・ホモ・サピエンス誕生の150万年も前のものである。
「2001年、宇宙の旅」のオープニングに出てくるヒトザルはおそらくこの時代のものだろう。骨を道具として使い、集団社会生活をしている。
オルドヴァイの切り立った渓谷はアフリカ大陸を南北に縦断するグレート・リフト・バレー(大地溝帯、崖は深く地底をなす)の一角で、「人類はこの深い谷間で生まれた」といわれている。
渓谷の東側には広大なサヴァンナが広がる。渓谷は緑豊かで、ここには天敵もなく、バナナなどの果実は豊富で、植物の葉や根菜、小動物、昆虫など食料も豊富だった。しかし、なぜホモ・サピエンスは草原へと出てきたのだろう。サヴァンナにはライオンやヒョウ、ハイエナなど食肉獣が暮らしており、森林地帯よりはるかに危険をともなうのだ。
気の遠くなる歳月なので、気象条件とか環境異変とか理由はあると思うが、一番の原因はホモ・サピエンスの好奇心、探求心だったのではないか、というクライブ・フィンレイソン博士の推察(「そして最後にヒトが残った」(白揚社))に説得力がある。博士によれば、人類には本来的にイノベーター(革新派)とコンサヴァティブ(保守派)の二派があり、そのなかのイノベーターの一群が好奇心、探求心に駆られてサヴァンナに出、以後強固な二足歩行者となり、頭脳が発達し、今日の人類に至ったのでないか、というものだ。コンサヴァティブはそのままチンパンジーやゴリラの仲間として残るしかなかった。
やがて人類はふたたび好奇心に駆られ、ふるさとのアフリカを出て、見知らぬヨーロッパ、アジアへの大地へと旅を重ねてゆくのである。好奇心こそ今日の人類進化のキイであったようだ。新人類は元来、旅好きだったのだ。
さて宇宙への旅から人類の旅になってしまったが、今日AI産業は急激な成長を続けており、いつのまにかケイタイが全世界を支配してしまった。
今や世界の情報はたちどころに手元のケイタイで把握できる環境下にある。
世界はトラベラーにあふれ、情報は手元にある。
人類にとって新たな好奇心、探求心は、やはり宇宙へと向かうしかないようである。

人類の歴史を続ける。そこで猿人の次はネアンデルタール人となるが、「ネアンデルタール人が出てくる映画はないか、そんな映画はないだろうな」と、念のためケイタイのAIに聞いてみたら、それがなんとパッと出てきたのだ。あの「ナイトミュージアム」の第3弾「エジプト王の秘密」だった。
AIの凄さを再認識した。よほどの映画評論家でもない限り、その場でネアンデルタール人が出てくる映画など答えられないだろう。
映画ファンならご存知だろうが「ナイトミュージアム」は2006年のヒット作で、次々に続編が作られている。夜になると蝋人形や化石恐竜が大騒ぎするという世にも不思議なミュージアムの物語で、実際のニューヨーク自然史博物館を舞台にして、しがない夜間警備員の主人公・ラリーが活躍するというコミック・ファンタジーだ。
第3作目は展示物らが騒ぎ出すのはエジプトの「魔法の石板」に原因があり、それが輝くと彼らは活躍し、黴が生えて曇ると蝋人形らの生命力が失われてゆく、ということをテーマにしている。
巻頭のプラネタリウム完成記念式典のドタバタ騒ぎが終わると、蝋人形らは急にこわばり、生命力が途絶えてゆく。慌てたラリーは前の夜間警備員を訪ね、その原因をつきとめると、かつてエジプトの砂漠で秘蔵されていた石版は王宮から持ち出すと災いをおこし、やがて持ち出した者たちは死ぬ、というのであった。その秘密はロンドン博物館に秘蔵されている王が知っている、というのでラリーは監督官を説得し、息子、博物館にいるアクメンラー王子とともにイギリスへ向かった。
この時ラリーに同行するのはセオドア・ルーズベルトとインディアン娘のサカジャウィア、小人のローマ兵のオクタヴィウスと西部男のジェッドのいつもの顔ぶれだが、ここで登場するのがネアンデルタール人のラーであった。ラーの風貌はといえば、ボロの衣服を纏い、髪はぼうぼう、腰には白骨を武器につけている。彼はラリーとそっくりに造られているため、ラリーを「パパ」と呼んでなつくことになる。ラーは知恵遅れというか単純バカとでもいおうか、消火器のカスを食べ、ラリーが扉の閉鎖を命じると、ラーは両手で扉を押したまま、いつまでも同じ格好を続け、次の命令を待つという幼稚さだ。
ところがラーには野生的な魅力があった。そのラーに惚れ込んだのは渡航先のロンドン博物館の警備員、太っちょ娘のティリーだった。ラーのおかげで一行に好感をもったティリーは退屈しのぎもあってラリーらを入館させた。
さてロンドン博物館に乗り込んだ一行は、八岐大蛇(やまたのおろち)のようなソウリュウや恐竜化石のトリケラトップスに攻められたり、アーサー王の円卓の騎士・ランスロットに妨害されたりしながら、やっとの思いで王の元へたどり着き、アクメンラーは父母と感激の再会をするのであった。ラリーが石版の「謎」を聞くと、石版は月光を浴びると、生気が蘇るという。
そこでラリーは石板をニューヨークへふたたび持ち帰るべきかどうか、思案するが、同行者らはアクメンラーが両親とともにいられるよう願い、ラリーはその意見に従い石板をロンドンにおいてくる。
ニューヨーク博物館の仲間らはふたたびただの蝋人形となってしまった。しかし三年後、ロンドン博物館とニューヨーク博物館で共同イベントが催され、石版はニューヨークに戻ってきた。蝋人形、化石たちはふたたび息を取り戻し、ラリーはその様を見て幸福な時を過ごすのだった。
ロンドン博物館の女性夜間警備員のティリーはラーに再会し、二人は結ばれるーー以上が映画のストーリーである。
少し人類のお勉強をしてみよう。
チンパンジー、ゴリラ、オランウータン、ヒトは大きく霊長類とされている。
気が遠くなりそうだが、約500万年前にヒトはチンパンジー、ゴリラから分派して猿人が生まれる。猿人はサルとヒトとの中間的存在で、アウストラロピテクス・アファレンシス(発掘当時流行っていたビートルズの歌にちなみ「ルーシー」と呼ばれる)やホモ・ハビリス(前述したオルドヴァイ峡谷でルイス・リーキー博士が発掘した。ハビリスは「器用な人」の意味)らを経て、150万年前くらいに原人(ホモ・エレクトゥス)にとって代わる。原人は身長が120cmくらいしかないルーシーらに比べ体格が大きく、二足歩行が通常となり、石器をもちいた。昔教科書で習った北京原人、ジャワ原人が知られるところだ。
ピエール・プール原作のヒット作「猿の惑星」(1968、フランクリン・J・シャフナ―監督)を思い出す。映画はゴリラか猿人が知恵をもち、人間らを狩り、奴隷としている。猿とヒトはDNAではほとんど同じで、ただ本来ヒトには猿にはない知性があるはずだった。ところがこの惑星ではヒトが知恵をなくした代わりに猿が知性を発達させ、ヒトをコキ使っているのだ。猿が支配する惑星は、愚かな人間が文明の果てに核戦争で荒廃させてしまった地球であった、というオチであった。
原人に次いでネアンデルタール人が現れる。「ナイトミュージアム」のラーである。
約30万年前から出現し、ヨーロッパ、中央アジアで発掘された。当時は氷河期で、ネアンデルタール人は洞窟を主な住まいとしており、体格はわれわれ現世人類(ホモ・サピエンス)より逞しく(身長180cm以上あった)、頭も大きく、脳容量はわれわれの平均容量1400CCより大きかったようだ。毛皮を纏い、マンモス、トナカイ、ウマ、サイを狩猟していた。石器の利用も進み、剥片を製作した石器をナイフ、スクレーパーなどに利用していた。言語も使っていたようだ。
とすれば、映画のラーは背丈、体格を除けば実際のネアンデルタール人に近いかもしれない。問題は映画では女性警備員のティリーと結ばれるが、果たして現世人類との交流、交配があったか、どうかということである。
われわれ現生人類(ホモ・サピエンス)は約20万年前にアフリカで誕生した(最近研究が進んでおり、参考文献により南アフリカだったり東アフリカだったりする)。9万年前にアフリカ大陸を出て、中近東を経て、6、7万年前に世界へと拡散した。日本には4、5万年前に上陸した(沖縄の港川人が最古といわれている)。
ネアンデルタール人は狩猟生活者で、総人口は少なかった。これまでの説では寒冷期の洞窟暮らしで自然消滅したとか、ホモ・サピエンスが増大して、ネアンデルタール人を追いやり絶滅させた、とかが主流だったが、最近の研究ではネアンデルタール人とホモ・サピエンスは同時期に暮らしたことがあり、そこでは交流や交配が行われたというのが主流である。
ならばこの映画のラーとティリーの出会いと恋愛は非現実なことではない。監督はそれを見通して、この映画の構成を考えたのだろう。(最近の研究では現世人類のDNAのなかの**%がネアンデルタール人のゲノムがあり、交配は確実なものとされている)。
体格的にも脳の容量も大きかったネアンデルタール人らに代わり、なぜ現生人類が生き残ったのか? 小型で素早く、長距離を走れ、死肉も平気で食べる生活能力がわれわれの方が優れており、環境が激変する時代にはのろくて、大ようなネアンデルタール人は向かなかったようだ。ようは現生人類ははしっこく、テキパキと実働レベルで優れていたようである。
しかし、ヘンリー・ジー博士(「超圧縮地球生物全史」(ダイヤモンド社))によると、
「今後数千年のあいだに、ホモ・サピエンスは消滅するだろう」
と、予言している。
人類の人口増加による環境破壊、気候変動、森林減少などにより地球はもはやそのダメージに耐えられなくなり、人類の食糧、資源(石油、石炭)、飲料水の供給は不可能となるからだ。世界人口は紀元前1万年には450万人しかいなかった。それが今は82億人を超える。博士は「人口は21世紀末にピークに達し、そこから先は次第に減少し、やがて消滅するだろう」と説いている。今さら反省してももう遅いようだ。
現生人類が消滅する数千万年の間に、ホモ・サピエンスから別の省エネ型、地球に優しい新・現生人類が誕生する可能性はあるだろう。前述した「2001年、宇宙の旅」の赤ちゃんは、その出現の予告だったのかもしれない。
随分前のことだが、フランス南西部、ヴェゼール渓谷にあるラスコー洞窟へ行ったことがあった。
新人類(ホモ・サピエンス)の代表、クロマニヨン人の遺跡である。約2万年前、氷河期後期の遺跡で、彼らはこの洞窟で、素晴らしい動物絵を遺していた。全長200mはあろうか、3つの部屋に分かれた薄暗い洞窟の壁面には野生動物の絵画が躍動感溢れる筆致で描かれていた。なかでも勇壮なオオツノジカ、黒い大きな腹の牝牛、褐色のバイソンなど彩色され遠近法のように重ねられた手法の壁画には現代絵画に近いアート感覚を思わせた。
狩猟民族だった彼らにとって動物たちは神が与えてくれた惠みだったに違いない。同行のガイドの説明では、クロマニヨン人は暗い洞窟で石製のランプを使い、寒さに耐える獣皮の衣装を纏い、女性は顔に刺青のような化粧をしていたという。彼らは死人を遺棄せず、埋葬し、シャーマンなる呪術師がいたのではないか、動物らは自然信仰に関係がある宗教画ではないか、との説明を受けた覚えがある。
そうか、われわれ新人類とネアンデルタール人との差は芸術する心なのだ、とその時思った。神々に感謝する心をもち、祈ることが芸術を生み、それが徹底的な旧人類との差となったのだ。
1万年前には氷河期が終わり、氷河が解けて海水面が上昇、地球は温暖化し、それまでの砂漠は草原となり、植物は花を咲かせ、人類は洞窟から地上に出て繁栄した。
日本の縄文時代はちょうど1万年前にはじまった。縄文人は世界でも稀な最古の土器(縄文土器)をつくりはじめた。
アートによって、人類は目覚め、新しい世紀を創造したのだ。
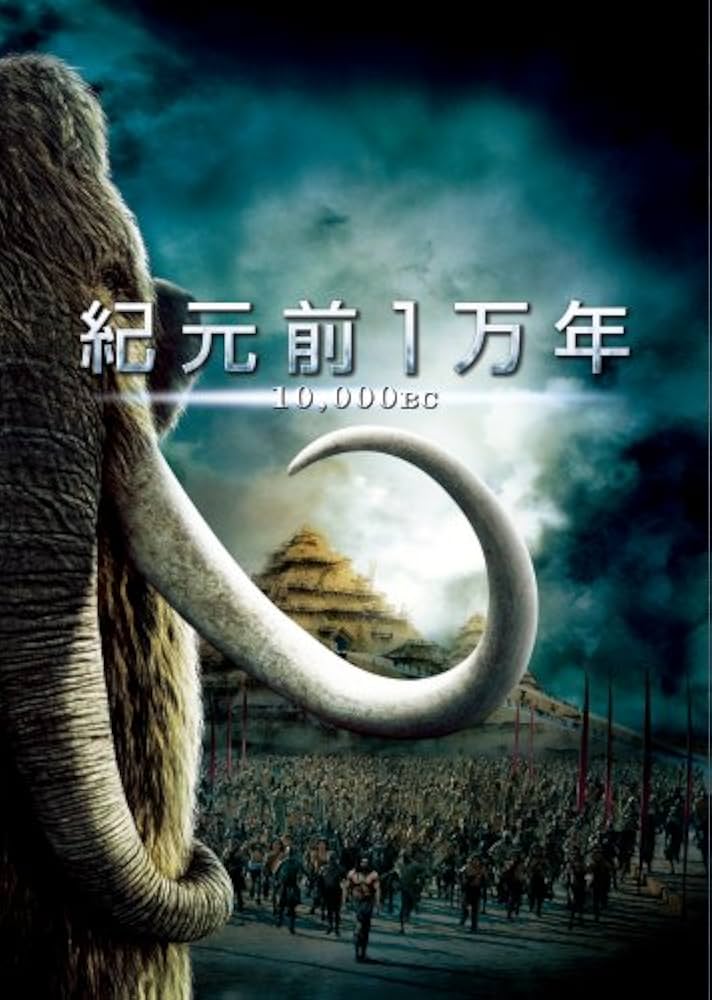
猿人、ネアンデルタール人と辿り、次なるは縄文人あたりの映画はないか、と捜したら、「紀元前10000年」というどんぴしゃの映画タイトルが出てきた。ただし、これは日本の縄文時代ではなく、世界の辺境が舞台の映画だ。
アクション、パニックもの、宇宙SFで知られるかのローランド・エメリッヒ(「インデペンデンス・デイ」「デイ・アフター・トゥモロー」などがある)の監督作品で、なんだか彼自らが楽しみながら作ったような娯楽映画。紀元前10000年あたりを設定しており、狩猟民族やマンモス、サーベル・タイガー、ピラミッドなどが出てきて奇想天外の面白さがある。
まずはストーリーを紹介しよう。
地球の片隅で狩猟採集生活を営むヤガラという名の部族がいる。
ヤガラ族の主要な収穫物はマンモスだ。ところがマンモスは年々減ってきており、ヤガラ族の暮らしを追い込んでいる。集落にはシャーマンの巫母(みぼ)がおり、その老女の予言によれば、最後のマンモスの狩りの後、「四本足の悪魔」に村は襲われる。しかし、やがて若者が村を救う。その若者はマンモスを倒した者で、族長となり、青い目をした少女・エバレットを妻にするだろう、というものだ。
主人公のデレーは少年の時、族長だった父親が村を去ったため、村の少年からは「裏切者の息子」と疎んじられつつ成人した。しかし最後の狩りの時、幸運にも巨大マンモスを倒した。そこで彼は族長のシンボル・白い槍を渡され、エバレット(娘に成長している)と婚約するが、正直者のデレーは父親の友人で、族長となっているティクティクにマンモスを倒したのは偶然で、勇気ではなかったと打ち明け、白い槍を族長に返した。
巫母の予言通り、「四つ足の悪魔」は村を襲った。四つ足の悪魔とは馬に跨った奴隷狩りの他民族だった。彼らは周辺の部族を襲い、奴隷狩りを続けている。この時村の若者やエバレットもさらわれた。
デレーとティクティクは部族の仲間を取り戻すため、騎馬民族を追跡した。
ナウ族?の集落に近づくと、彼らは当初敵意を露わにしたが、デレーが突然現れたサーベル・タイガー(「牙」と呼ばれる)に襲われない様子を見て、“牙と話す男”として尊敬される。族長の**はヤガラ語を話し、以前この村を訪れ、友人となったヤガラの男の話をした。その男こそデレーの父親だったのだ。デレーの父親はナウ族と連帯して、騎馬民族の襲撃から村を守ろうと図ったが残念なことに彼らに捕まり奴隷となってしまった。デレーとティクティクはなおも騎馬民族を追跡する。その間に**は周辺の部族を結集させていた。
騎馬民族は“巨大な鳥”(帆を張った船)で消え去った。デレーらは死の砂漠を乗り越え、大神の支配する敵の王国へ侵入する。そこでは巨大なピラミッドを建造中で奴隷やマンモスが働かされていた。デレーは王国の牢獄に忍び込み、奴隷たちを味方にして、反乱を企てる。そこへ***が集めた各部族らの兵士がなだれ込む。
神官にかしづかれた大神は敗色が濃くなり、デレーら反乱軍が引き上げればエバレットを渡すと交換条件を出した。しかし、デレーはそれを拒否し、手に持った白い槍を放つと、槍は大神の胸を貫き、大神は倒れた。
「神などいない。死んだのだ!」――デレーが叫ぶと、部族の兵士、奴隷だった者たちが力を得、ピラミッドの王国を滅ぼすのだった。
最後にやっとデレーとエバレットは結ばれる。
*****
奇想天外、荒唐無稽なアドヴェンチャーといえばそれまでだが、原作者や監督の考案した物語の背景を推察してみるのも一興だ。ドイツ出身で、インテリのエメリッヒ監督を思えば、時代背景はそれなりに考えている、と思われるからだ。
さて舞台はどこか? 映像の砂漠、草原を鑑みると、中近東、北アフリカあたりであることは想像に難くない。ヒーローが白人系ではなく、周辺部族に黒人が多いことからも、おそらくシリア、レバノンあたりの設定ではないか。このあたりは”肥沃な三日月地帯“で、かつてはガゼルの群などが生息し、狩猟生活には事欠かないはずだ。日本では縄文時代が10000年くらい続くが、環境がよければ民族はそのまま変わらぬ暮らしを続けるのは歴史の示すところである。日本は気候が温暖で、湿潤だから植物は育ち、野生動物も多い。人々はさほど苦労しなくとも平穏に暮らせたはずである。時代の変化が激しくなったのは文明がはじまってからだ。映画では主人公のデレーらはパンではなく肉を食べているから狩猟採集生活だったことを暗示させる。紀元前1万年というのはちょうど氷河期の終わりころで、人類が洞窟から出て、草原に獲物を追った時代である。
マンモスは氷河期、11万年前から間氷期に入る1万年前まで生息していた。紀元前10000年は地球温暖化でマンモスが絶滅する頃で、映画では「最後の狩り」となっているから、これも照合している。
そうなると砂漠はシリア砂漠あたりが想定される。瓦礫の多い砂漠だが、昔から遊牧民らは行き来しており、パルミラの遺跡もある。人跡未踏の砂漠地帯もあるだろうが越えられないことはない。だとすると“巨大な鳥”の浮かぶ河はユーフラテス川だ。ユーフラテス川はチグリス川と並走しており、両河川の流れるメソポタミアは古代文明の発祥地で、ナイル川(エジプト)、インダス川(インド)、黄河・揚子江(中国)と並び、世界の四大文明の発祥地として知られるところだ。
そこで考えられるのはウルカ、ウルの古代文明遺跡だ。狩猟採集時代から農耕文明時代へいきなり映画は5000年ほどタイムトリップすることになる。映画だから、そんな芸当は朝飯前だろう。
ウルカはメソポタミア文明の中心地で、そこには王がいた。王は巨大なピラミッドのような神殿をもっており、神官がかしづき、軍隊をもち、多くの奴隷が使役されていた。
デレーは5000年をタイムトリップして、メソポタミアの王宮へ進撃し、王を槍で殺し、王が神ではないことを実証して、エバレットを勝ちとることになる。
まさに時代の逆転劇だ。勧善懲悪は映画の原則とでもいおうか、観衆は弱き者、正義を貫く者を応援する。馬と鉄器を使う奴隷狩り(高等)民族にこん棒と投石の少数民族が勝ってしまったのだ。
ここで思い出すのは、かの大航海時代、スペインのコルテス将軍下のわずか176名の兵士がインカ帝国の何万もの兵士と戦って、勝利し、金銀を強奪し、インカ帝国を滅ぼしてしまった歴史の真実だ。鉄と馬という文明にまたたく間に滅ぼされてしまったインカの王と軍隊。文明に対して石とこん棒で戦ったような未文明のはかなさ、民族の無念をこの映画は逆手にとって気持ちよく晴らしてくれる。縄文人は渡来の弥生人(文明人)に滅ぼされるが、たまには文明の流れをひっくり返す”オトギ話“があったもよいではないか。この映画は時代を逆手にとったわけだが、たまにはこうした文明への反逆があってもよいのである。

「女なんていっぱいいるさ、あわてることないよ」
物語は1920年代のモンタナ州、フライフィッシングを通じて結ばれた父親と二人の兄弟をめぐる話である。原作者のノーマン・マクリーンは大学教授で『マクリーンの川』という原題の本を自費出版で大学の出版部から少部数で出した。ところが本の評判は口コミで広がり、隠れたベストセラーになったという。長老派教会の牧師だった父親は二人の兄弟に聖書の教えとフライフィッシングを教えた。やがて兄のノーマンは東部のエリート大学に進学し、卒業後はシカゴ大学の文学部に招かれる。一方、弟のポールは地元の大学に進み、新聞記者となった。知的で物静かな兄と行動的で野性味溢れる弟の対比は聖書のカインとアベルの兄弟物語を想像させる。独立記念日のパーティで出会ったジェシーにノーマンは一目惚れし、シカゴ赴任と同時に二人は婚約するが、それを聞いたポールが兄に言うセリフが上記のものだ。やがてポールは酒とポーカーに走り、莫大な借金を背負い、道を誤り殺される。すでに年老いた兄は、流れる川にかつての弟の天才的なキャスティングの姿をしのび、川の流れに真実が眠っていることを覚る。
スルー・イットの「It」が何を意味しているのか、長らく疑問だったが、今回見直してみて、それが「時」であり「時代」であったことに気づいた。川は家族の物語の間を、今も変わらず、黙々と流れているのである。
ロバート・レッドフォードが監督し、ブラッド・ピットを起用したことで、ピットはいきなり銀幕に躍り出た。激しくはかない線香花火のような人生を送ったポールの役はピットそのもので、その笑顔はいつまでもぼくらの心を捉えて放さない。ジェームス・ディーンがそうであったように永遠の青春の姿なのである。
モンタナへは二度行った。舞台となったミズーラの町の近くの牧場にホームステイしたことや映画のロケ地となったギャラティン川でもフライフィッシングをしたことを思い出す。映画を観て訪ねたわけではなく、いずれもフライロッドを携えての、釣りの旅のことだった。映画が上映されたのは1992年、ぼくの『地球鱒釣り紀行』(新潮社)が出版されたのは1997年だから、その頃ぼくは海外取材にかこつけてパックロッドをスーツケースにしのび込ませ、夢中になって地球を駆けづりまくっていた。
アメリカのカントリーサイドを舞台にした映画が好きだ。『モンタナの風に吹かれてThe Horse Whisperer』(ロバート・レッドフォード)、『アメリカ、家族のいる風景Don’t Come Knocking』(サム・シェパード)はモンタナが舞台、また雄大な風景をバックにした西部劇も多く『ワイルドレンジOpen Range』,『レヴェナントThe Revenant』(レオナルド・ディカプリオ)もモンタナが舞台だ。
抜けるような青い大きな空と澄み切った渓流の流れに心は洗われるようである。